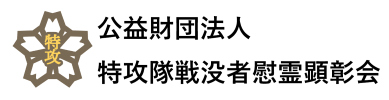第一編 特別攻撃隊の戦闘 第4章 地上戦闘における特攻
 1. 空挺特攻
1. 空挺特攻
総論
体当たり攻撃は、決して空や海だけのものではなかった。序章で述べられている玉砕の島々においても、その他の激戦地においても壮絶な体当たり攻撃が行われたであろう。例えば沖縄戦においても、比島戦においても、対戦車地雷を抱いた兵が敵戦車に体当たりし、ビルマ戦線では壕にひそんだ兵が爆弾と共に炸裂し、頭上の戦車を破壊した。その一身を犠牲にして友軍の危急を救う忠烈は、まさに特攻である。しかしその詳細と氏名を明らかに出来ないのが残念である。
ここでは、組織的かつ大規模に決行された空挺特攻と戦車特攻を、地上戦闘における特攻の代表としてかかげる。
一. 空挺特攻
空挺部隊は、極めて危険度の高い部隊と目されていた。それは、落下傘やグライダーを使って空から降りるという技術的な問題だけでなく、地上進攻部隊と合流できないときは、やがて全滅してしまうというおそれがあるからである。
危険度が高いからというだけでは、特攻隊と称することはできないが、初めから地上の友軍と合流できないことを承知の上で出撃する場合は、爆薬をつけて敵に体当たりをしなくても、これを特攻隊と称して、いささかも不都合はなかろう。
そのような考えに立つと、空挺特攻の萌芽は割に早い時期にあった。戦局の焦点が東部ニューギニアであった18年4月頃、戦場における彼我の戦力はまだ互角だった。その勢力圏の中間に横たわる脊梁山脈の中に、ベナベナ・ハーゲンという高原地帯があった。その地区に敵が飛行場を設定中であることを、我が方は空中偵察によって発見した。そこで、空挺部隊を使ってこれを奪取しようという案が台頭し、当時宮崎県の唐瀬原基地に帰っていた第1挺進団に動員が下令された。
挺進団の諸隊はペリリュー島に集結し、挺進団長河島慶吾大佐は団司令部をニューギニア北岸のウエアクに進め、作戦準備にかかった。ところが、第18軍や第6飛行師団で仔細に検討してみると、空挺部隊を降下させることは容易であるが、地上部隊をそこまで進めることは、地形上極めて困難である。たとえ軽装備部隊を派遣して提携しても、後の補給は一切人力による担送に頼らなければならない。そのようなことで、空挺作戦の計画は消滅しかかったが、挺進団側には遥々内地から出て来て、引くに引かれぬ騎虎の勢いがある。地上部隊が進出しなくても、所在の敵を撃滅し、その後は遊撃戦を展開するという案を具申した。しかし、まだその頃は、このような特攻的空挺作戦を行うような考えが高等司令部にはなく、遂に陽の目を見ずに終った。これが一年余り後のレイテ作戦の頃になると様相は異なる。
1 薫空挺隊
レイテに敵が上陸したのは19年10月20日で、これに対しマニラに本拠を持つ我が第14方面軍では、第1師団、第26師団と、次々に増援部隊をレイテに送り込んだ。ところが、11月10日にオルモック湾に到着した第26師団は上陸に先立ち敵の航空攻撃を受け、輸送船を沈められて装備一切を失った。
そこで、敵航空の活動を抑えるため、その中枢と目されるブラウエン飛行場群に空挺特攻隊を着陸させ、たとえ一時的にでもこれを封殺しようとはかった。その頃新たにフィリピン方面に派遣された第2挺進団はルソン島に到着しつつあるところで、まだ使える態勢にはなっていなかった。それがため、薫空挺隊と命名された特殊部隊が起用されることになった。この部隊のことは、先ず母隊となった遊撃中隊から説明しなければならない。
昭和18年12月24日、台湾軍は遊撃第1、第2の両中隊の編成を命ぜられた。両中隊とも総員一九二名、兵の人数は一五二名だった。その一五二名の兵のうち、通信と衛星の特技者を除きあとは台湾の高砂族をもって編成した。従って高砂族の兵士は中隊で一四〇名位だったと思う。将校、下士官は勿論内地人で、しかも陸軍中野学校出身者をもって充て、ジャングル内の遊撃戦専門部隊として訓練した。
台北の湖口演習場で約半年訓練し、19年5月28日高雄出発、ニューギニアに向かう筈だったが、途中で変更になり6月2日にマニラに上陸した。第2中隊は間もなくハルマヘラ島に移り、その後モロタイ島で大活躍することになる。一方、第1中隊はルソン島に残り、リパに在って訓練をしていた。
当時フィリピン駐在の村田大使の書いた「比島日記」には、11月13日に寺内総司令官を訪ねて聞いた話として、高砂兵部隊のことが出ている。爆弾を背負って敵中に突入する部隊だと書いてあるので、そのような特攻的戦法の訓練をしていたのであろう。敵航空基地に対する殴り込み作戦にこの部隊を使うことが決まってからのことか、あるいはそれ以前からこの種の訓練をしていたのかはよく判らない。
レイテ作戦が始まって間もない頃は、カモテス海で我が船団を攻撃する敵機はモロタイ島に基地を持つB-24爆撃機だけだったので、この遊撃中隊をモロタイ島の飛行場に強制着陸させようとした。ところが11月下旬になると、レイテの敵飛行場の整備が進み、この方が急を要することになった。レイテ島内で敵が使っている飛行場は次の五つだった。
( )内は11月17日偵察結果の在地記数。
タクロバン(約一〇〇機)
ブラウエン北(約一〇〇機)
ブラウエン南(約一〇〇機)
サンパブロ(少数)
ドラッグ(少数)
第4航空軍では、遊撃第1中隊の一部を、飛行第二〇八戦隊の零式輸送機(DC-3)に乗せ、ブラウエンの両飛行場に強行着陸攻撃を実施させることになった。この命令が出されたのは11月22日で、部隊を「薫空挺隊」作戦名を「義号作戦と呼ぶことになった。
義号作戦は26日に決行された。中重夫中尉以下四十数名の薫空挺隊員は、第二〇八戦隊の桐村浩三中尉以下八名の操縦する輸送機四機に搭乗し、夜間リパを離陸してブラウエンに向かった。月齢は十日である。零時頃ブラウエンに着陸する計画だったが、その後の行動は不明な点が多い。
一機はその頃まだ我が方が確保していたバレンシヤ飛行場に着陸し、第26師団と行動を共にしたことは確かである。
零時過ぎ頃、オルモックの軍司令部から東方の山系を望むと、盛んに火の手が揚がるのが見えたというし、一時過ぎにブラウエン上空に我が偵察機が進入したが、いつもの激しい対空砲火はなかったという。
これだけの徴候では、ブラウエン飛行場に着陸成功し、戦果を挙げたと断定することはできない。米軍の記録によれば、ドラッグ海岸付近に二機着陸し、乗員が闇の中に消えて行ったという。多分これが脊梁山脈を越した三機のうちの二機であろう。その人々がどのような働きをしたのか、残念ながら明らかではない。
敵飛行場を襲撃した後は、ダガミ付近に潜行し第16師団に合流する計画だった。ジャングル内の行動に習熟している高砂族のことだから、ダガミまで辿り着いた者があるかもしれない。義号作戦から十日後、高千穂部隊(第2挺進団の部隊)がタクロバンに降下し、百人以上の者が第16師団と合流した。しかし、この人々の最後も明らかでないほどであるから、少人数の部隊の最後は知る由もない。
なお、薫空挺隊を差し出した後の遊撃第1中隊の主力は、三陣に分かれてマニラを発ち、船でレイテに向かった。中隊長尾山盛大尉以下の約一〇〇名は途中で海没戦死したが、それ以外の四九名はレイテに上陸して戦闘に参加した。その中には数名の生存者がいたが、薫空挺隊の最後はわからない。
遠い先祖以来日本国に生を受けた者が、国家非常に際し命を捨てるのは当然のことであるが、国家間の勢力の変遷で一時的に日本人となった高砂族の兵士が、このように名もなく死に、日本人の記憶から消えるのは誠に申訳ないことである。厚生省援護局に保管されている名簿をみると、当人は日本名で記載されているが、留守担当者欄には片仮名の名前が記入されている。靖国神社には合祀されているが、御遺族にはそのことが伝わっているのであろうか。

2 高千穂降下部隊
高千穂部隊の名で知られている第2挺進団は、レイテ地上戦況の退勢を挽回するため、19年12月6日レイテのタクロバン地区(レイテ湾に面する平野部の総称)の数個所に空挺作戦を行った。この日降下した者四百数十名に一人の生還者もなかったが、これは彼我の戦力が隔絶していた結果であって、この部隊全部を特攻隊と称することは当たらないと思う。しかし、その中には初めから地上部隊と提携の望みがない目標に、それを承知の上で出撃した部隊がある。しかも、その目標は上から命ぜられたものではなく、実行部隊の強い要望によって加えられたものである。従って、この部隊こそ正に特攻隊と言うべきであろう。
レイテの守備を担当していた第16師団は、19年10月20日敵の上陸を迎えたが、戦力の差余りにも大きく、残存の部隊はダガミ西方高地に封じ込められてしまった。マニラから増援した第1師団は、11月1日オルモックに上陸し、カリガラを経由してタクロバン地区に出ようとしたが、リモン峠で敵と四つに組み、やがて気息奄々となってしまう。その間、当面を担当している第35軍でも、他の島から為し得る限りの兵力を差し向けたが、戦勢は日に日に急迫を告げていった。マニラに在る第14方面軍の指導で、第35軍では11月10日にイピルに上陸した第26師団を、脊梁山脈を越えてブラウエン付近に進出させ、タクロバン地区に地歩を回復しようと企図した。これを「和」号作戦と呼ぶ。
「和号作戦」に呼応して第4航空軍では、新たに指揮下に入った第2挺進団を第26師団の進出に先立ちブラウエン地区に降下させようとした。これを「テ号作戦」と呼ぶ。ブラウエン地区には、前章にも書いたが、ブラウエン北、ブラウエン南、サンパブロの三つの飛行場があり、盛んに活躍しているので、これを封殺するために薫空挺隊による「義号作戦」が行われたことは前述の通りである。今度の「テ号作戦」はこれとは異なり、そこに居座って地上部隊と提携しようというものである。
第2挺進団長徳永大佐が、第4航空軍からこの作戦の内示を受けたのは11月22日で、そのとき掌握していた部下部隊は挺進第3聯隊と挺進飛行第1戦隊であった。挺進団がクラーク基地でブラウエン降下作戦の準備を進めている途中の26日に「義号作戦」が行われた。次いで30日には後続の挺進第4聯隊が追及して来た。更に挺進飛行第1戦隊に、第2戦隊の一個中隊が配属され、輸送機は全部で四個中隊になるということを承知した。
挺進団では、ブラウエン降下作戦は従来から考えていた作戦形態であるが、敵の航空を制圧することがこの際緊要であるとするならば、タクロバンとドラッグに対しても一部を降下させたい。その部隊は収容の見込みがないにしても、「薫空挺隊」があのように使われたとなると、空挺の本流をもって任ずる我々が後れを取ってなるものかという考えが、聯隊や団司令部の幕僚の中から起きてきた。
そこで、徳永団長は第4航空軍に意見を具申し次のような部署を採った。
〇 ブラウエンの三飛行場には、第3聯隊長白井少佐指揮の二個中隊半を降下させ、引返して来た輸送機で反覆空輸し団の主力をこゝに注き込む。
〇 タクロバン飛行場には第4聯隊榊原大尉の指揮する一個小隊を輸送機二機で降下させ、同時に団司令部佐藤中尉の指揮する部隊を重爆二機で着陸させる。
〇 ドラッグ飛行場には第4聯隊宮田中尉の指揮する一個中隊を輸送機七機で降下させ、同時に第3聯隊竹本中尉の指揮する部隊を重爆二機で着陸させる。
海岸にある両飛行場に対し重爆の強行着陸を併用したのは、超低空で進入する強行着陸の方が成功の確率が高いと判断したかららしいが、輸送機の不足を補う意味もあった。この重爆は飛行第74、95両戦隊から差し出された。二つの強行着陸部隊は第3聯隊で編成しているが、特攻隊ということで志願者を募ったところ、ブラウエンの第一次降下に漏れた者が競って志願したという。
タクロバンとドラッグに降下する部隊を乗せるのは、後から挺進飛行第1戦隊に増加配属された第2戦隊の三浦中隊であった。挺進飛行戦隊は、過早にクラーク基地に進出して敵機の攻撃を受けることがないように、台湾の嘉義で暫く待機し、決行の前日にアンフエレス飛行場に飛来した。中隊長三浦浩大尉は、全般状況の説明を聞きこの任務を受けるや、敵後方の兵站中枢でもあるタクロバンでは、物凄い対空砲火を受けるであろう。その弾幕の中を低速で飛行し落下傘兵を降下させることは、万に一つも成功の可能性はないと判断したのだろう。輸送機も着陸してしまえと部下に指示したという。これは海中に撃墜されて浮遊中に敵に捉えられ、戦後帰還したある操縦者下士官の言である。また、輸送機は九機ともドラッグに着陸し、重爆は四機ともタクロバンに着陸するように変更されたともいう。
徳永団長はタクロバンとドラッグに向かう部隊を集め、飛行場の襲撃が終ったら死に急ぐことなく、ブラウエンかダガミまで潜行せよと訓示したという。これは同じように海中に撃墜されて捉えられた挺進第3聯隊のある下士官の証言である。
さて、「テ号作戦」は12月6日に決行された。強行着陸の重爆も入れて約四〇機の輸送機編隊は、一五四〇頃アンフェレス飛行場を離陸し、ネグロス島のバゴロド上空を経て、レイテ島南端を通り北上して目標に向かった。三浦中隊は南端の変針点で主力編隊から分進したが、主力編隊の搭乗者がブラウエンの少し手前で右方を見ると、三浦中隊は物凄い対空砲火の中を喘ぐように飛行していたという。結局一機も帰って来なかった。
ブラウエン地区に降下した部隊のうちで、北飛行場に降下した聯隊主力は、一時的飛行場を占領した。しかし、輸送機の損害が甚大だったことと、翌日敵が西海岸のイピルに上陸したことなどで後援続かず、撤退せざるを得なくなった。
タクロバンとドラッグに向かった部隊は、撃墜されたり着陸に失敗したりして、地上戦闘に入ったものは残念ながら一機もなかったらしい。両部隊とも海上に撃墜されて捉えられた者がいる。先ずドラッグに着陸しようとした輸送機の操縦者の話を要約すると、
≪パラオン島北部分進点を通過し、逐次高度を下げ、島の最狭部付近に達した頃、海上と陸上から物凄い対空射撃を受けた。地上にある対空火器は、一メートル間隔に配列してあるのかと思うほどの密度だった。海上には無数の艦船が浮かんでおり、その船が真赤く見えるほど打ち上げてくる。夕暮れが迫っていたが飛行機の四周に炸裂する砲弾は、目がくらむほどだった。そのうちに右翼を射ち貫かれて海上に墜落した。
輸送機から放り出されて海上を漂っていたが、肩と背中を負傷していたので精神朦朧とし眠ったり醒めたりしているうちに、翌日の午後敵の上陸用舟艇に引上げられた。僚機のことは何もわからない。≫
次は挺進第3聯隊でタクロバンの強行着陸隊の一員だった某曹長の話、
≪落下傘は着けずに救命胴衣だけで、全員が拳銃と手榴弾をもって重爆に乗り込んだ。座った場所からは天蓋を通して上空だけしか見えなかったが、目的地近くまで来たと思う頃、上空を見ると敵の対空砲火の曳光が物凄く、まるで打上げ花火を見るようだった。何発か機体に命中したような感じがし、そのうちに海上に着水した。
操縦者の指示で全員無事脱出し、飛行機は数分後に沈んだ。あたりは薄暗く、どの方向が陸か判明しなかった。水は温く救命胴衣のお陰で浮いているのは楽だった。よく泳げるものは勝手に泳いで行き、最後は四人になった。闇をすかしてみると、遠くに山があるようにも見え、大きな船のようにも見え、潮で流されていることは判った。
そのうちに夜が明けてみると、四方八方敵の軍艦ばかりで、上陸用舟艇らしいもので走って来て、自動小銃で撃たれ、もはやこれまでと観念していると、鉤で舟の中に引き上げられた。殺せ殺せと叫んだが殺されなかった。軍艦の営倉に入れられ、その後タクロバンの収容所に入れられた。通訳にそれとなく尋ねてみると、そのとき海上で捉えられた者は三人で、二人は豪州に送られたということだった。タクロバンの収容所には高千穂部隊の者は誰もいなかったし、終戦後も入って来なかった≫
米軍の記録によれば、タクロバン飛行場内に一機着陸し、地上に在った五機と衝突して炎上した。機内には日本の落下傘兵八名と乗員三名が死んでいたとなっている。別の一機が、タクロバン西北方に着陸し、乗っていた日本兵は駆けつけた米軍と激しく戦い全員が戦死したとも記されている。
このようにして輸送機九機と重爆四機に搭乗した特攻殴り込み作戦も、空しい結末に終った。精神力では到底補えぬほどの戦力の格差があった。

3 義烈空挺隊
部隊編成の経緯
昭和19年7月サイパンが敵に占領され、B-29による本土空襲が必至と見た大本営は、サイパンのアスリート飛行場を爆撃し、本土空襲を未然に防止しようとした。11月1日、初めてB-29が東京上空に偵察に飛来し、本格的な空襲が始まったのは11月24日である。これに対し我陸海軍航空部隊は、11月2日以降数次にわたり少数機で敵飛行場を爆撃したが、敵空軍の活動を封ずることはできなかった。そこで、空挺部隊をアスリート飛行場に着陸させ、敵戦略空軍に一大鉄槌を加えようと、11月27日、当時宮崎県唐瀬原基地にいた第1挺進団に、一個中隊の差し出しを命じた。
第1挺進団では、挺進第1聯隊から奥山道郎大尉の指揮する一二六名の一隊を差出したが、この人員の大半は奥山大尉が中隊長をしている第4中隊から出した。奥山隊の人員は教導航空軍司令部付ということになり、12月8日に豊岡に到着し、中野学校出身の将校八名、下士官二名を加え、ここに後に義烈空挺隊と命名された特攻隊が編成された。
この部隊は、敵飛行場に着陸してから活躍する部隊であり、中野学校出身の一〇名は、諜報の任務に就くため加えられたものである。これらを乗せてサイパンに強行着陸する飛行部隊として、諏訪部忠一大尉を長とする第3独立飛行隊が指定された。この飛行機は初めサイパンを爆撃するため鉾田飛行学校で編成した部隊で、百式司偵を改造した爆撃機を装備していた。機種が長距離爆撃に不適であったりして、未だ成果を挙げていなかったが、空挺部隊を乗せて強行着陸する任務に変更となり、浜松に移り九七重に機種改編し、人員の一部入替を行った。奥山隊が豊岡に到着した頃は、漸く操縦者が揃い訓練に入ったところだった。
不発に終ったサイパン特攻
奥山隊が豊岡に到着すると、既にB-29の実大模型が松林の中に出来ていた。それは丸太で骨組を作り、胴体や主翼の要部にはトタン板を張ったもので、地上からの高さは実物通りになっていた。訓練というのは、敵飛行場に着陸したならば誘導路を疾走し、B-29に飛びかかりこれを爆破する動作だった。爆破には次の方法を用いた。
その一つは、B-29の胴体の上に帯状爆薬を投げ上げて爆破する方法である。B-29の胴体の上面は地上から4米50位ある。これに投縄の要領で、帯状爆薬を投上げるのであるが、初めはなかなか届かない。特に背の低い者にはむずかしいことだった。しかし、連日猛訓練を重ねるうちに、帯の先についている砂袋の錘りが、やがて身体の一部のように目標に飛びつくようになった。
もう一つの方法は、長さ1米50程の棒の先に4瓩の爆薬が付いているものを、翼のつけ根に装着して爆破することだった。爆薬の上面にはゴム製の吸盤が取り付けてあって、これで翼に吸着する仕掛けだった。この方法は帯状爆薬よりは容易だったが、相手がトタンの一枚板ではなく、リベットの頭やジュラルミンの継目があれば、確実に吸着するかどうか、不安が残った。
どの方法も装着後点火して退避するのであるが、吸着爆薬については、確実を期するため保持したまま爆破すべきであるという提案もあったが、奥山は一人で五機を屠れといって、自爆案はとらなかった。
誘導路上を五〇〇米ほど一目散に駆け抜ける、その間射撃を受けても、一挙に目標のところまで走り込む。B-29の下まで飛込んだならば、すかさず例の爆薬を装着する。
点火管の紐を引き、点火を確認する。
30米許り後退して伏せる。
唯これだけの動作を、それこそ火が出るほどに激しく訓練した。一見簡単な動作でも、その中に奥義というものがある。やがて入神の域とでもいうほどになった。
奥山隊が豊岡に来て一週間ばかり経ったとき、第3独立飛行隊(以下三独飛と称す)が浜松から豊岡に飛来し、夜間訓練に入った。
3独飛の操縦者は爆撃隊出身である。爆撃の任務につく時は、それが極めて危険な状況で生還の確率が僅少であっても、爆撃隊の使命であると割切って欣然として出撃しているが、敵の飛行場に着陸して玉砕するということは、操縦者として釈然としないものがあった。それがためか奥山隊ほど士気が高くなかった。奥山隊は空挺部隊の伝統的気風が充溢しており、中隊長が先頭で斬り込むということで、誰一人ためらう者はなかった。
3独飛の方も、豊岡に来てから「飛行隊は敵B-29を奪取し、これを操縦して帰還すべし」という任務が付加され、撃墜した飛行機から入手した取扱説明書の翻訳したものが渡され、その可能性は極めて少ないにしても、士気は高揚してきた。しかし、一、二〇〇粁の洋上飛行の後硫黄島に着陸給油し、それから更に一、二〇〇粁を飛び、しかも夜間超低空でサイパンを目指し、敵飛行場に着陸するということは、当時の航法器材では並大ていの技量ではできない。初の計画ではクリスマスの前夜決行を目途としていたが、3独飛の現在の練度では無理と判断された。
年が明けて、B-29による我が本土空襲は激化した。それと共に硫黄島も度々艦載機の攻撃を受けるようになった。第6航空軍(12月26日教導航空軍は第6飛行軍となる)では、遅れると硫黄島が使えなくなることを恐れ、1月13日、奥山隊を浜松に招致し、最後の準備を整えた。その頃硫黄島は連日空襲を受けていたが、それでも機を見て出撃しようと、17日には準備一切を整えて出撃態勢をとった。しかし、硫黄島からは着陸不能という連絡しかなかった。それから22日まで毎日待機したが、遂にその機を得ず、22日以降待機を取りやめ、30日になって本作戦中止の決定をみた。
挫折
奥山隊は傷心を抱いて古巣の宮崎県の唐瀬原基地に帰り、3独飛の方は依然浜松に留って部隊の錬成に励んだ。奥山隊には最終的に不時着生残りがいるので、この頃の事情を知ることができるが、3独飛の方は生存者がなく不明の点が多い。両部隊ともサイパンという目標は失ったものの、依然特攻隊として第6航空軍直轄のままになっていた。
2月19日、敵は硫黄島に上陸した。米軍は一週間で占領するつもりだったが、守備隊の強靭な戦闘によって、3月に入っても主陣地は我が方が確保していた。しかし、島内の二つの飛行場を敵が使い始め、小型機が多数進出し、更にB-29の緊急着陸場にも使っていることが判明した。そこで大本営では義烈空挺隊を使ってここを攻撃しようと、3月12日西筑波飛行場に招致した。
我が爆撃機の行動圏内の敵飛行場を攻撃するならば、爆撃法の工夫をすればよさそうなものを、何も特攻隊を着陸させる必要があろうかと思うが、奥山隊は喜び勇んで西筑波に移った。今度はサイパンと違い敵戦闘部隊の真唯中に飛込んで行くので、戦法も工夫して猛訓練を始めた。ところが、またも取り止めとなった。3月25日、硫黄島の栗林兵団長以下最後の突撃を敢行し玉砕してしまったからだというが、大本営が義烈空挺隊の使い方について、真剣に考えていたのかどうか疑わしい。
奥山隊はまたもや失意のうちに唐瀬原基地に帰り、3独飛は依然浜松で錬成を重ねることになった。
豊岡や西筑波にいて身近に空襲を体験し、激しい闘志を燃やしているときは迷いはないが、目標を失い、その頃まだ平穏な日向の片田舎にあって、しかも特攻隊という名を負い続けていることは、堪え難い思いだったと、奥山隊の生き残りの者は述懐している。



沖縄特攻作戦
沖縄に敵が侵攻したならば、我が陸海軍航空部隊は、総力を挙げて敵を洋上に撃滅する方策を立てていた。これがため陸軍の第6航空軍は聯合艦隊司令長官の指揮を受け、陸海軍ともに特攻を主体とし、陸軍は敵輸送船に、海軍は空母を主とする艦艇に体当たり必殺の攻撃を行う考えだった。
沖縄を守る第32軍は、たとえ敵の上陸を許しても、陸上の飛行機だけは飽くまで敵に使わせないようにして、我が航空決戦を容易にすることを、航空側は地上軍に期待していた。
ところが、第32軍は初め本島に三個師団と一個混成旅団を持っていたが、前年の秋一個師団を台湾に引き抜かれたので、主陣地を宜野湾東西の線まで下げ、北(読谷)、中(嘉手納)の両飛行場を、陣前に取り残すという配備に変更してしまった。蟹は体に似合った穴を掘るというが、第32軍としては止むを得ない配備変更で、大本営の空陸の統合された指導のないまま、4月1日敵の上陸を迎えた。
敵は嘉手納海岸12キロの正面に、先ず四個師団をもって上陸して来た。第32軍はかねて計画してあった通り、嘉手納付近では警戒部隊をもって軽戦を交えた後、首里を中核とする主陣地に立て籠り、敵は上陸第一日に北、中両飛行場を手に入れた。
我が陸海軍航空部隊は、集中の遅延によって立ち上がりに若干の後れはあったものの、特攻を主軸として敵艦船に対し反覆猛攻を加え、相当の成果を収めた。今までの例では敵空母艦隊は十日間位作戦すると一旦整備補給に退るので、その時期を捉えれば戦勢挽回の望みがあると踏んでいた。ところが、敵は4日には奪取した飛行場に戦闘機部隊を推進し活動を始めた。こうなると、我が特攻機は目標上空に到達する以前に敵戦闘機の要撃に遭い損害のみ多く成果が挙らなくなった。第32軍は聯合艦隊司令長官の要請や大本営の指導を受けて、二回ばかり攻勢に出たが、司令部内の意見を不一致なども禍して、敵の飛行場使用を覆すには程遠いものだった。
4月15日、陸海軍航空部隊は選抜した戦闘部隊二一機をもって、薄暮敵飛行場を制圧し、その機に乗じ晩から翌日にかけて特攻攻撃を行ったところ、多大の戦果があったと判断された。そこで地上部隊が飛行場を制圧することをしないならば、航空が自らの手でたとえ一時的にでも飛行場を抑え込んでしまうことを企図し、義烈空挺隊の起用を思いついた。
義烈空挺隊は第6航空軍に所属していたが、その使用については大本営の認可を要するとされていた。第6航空軍では熱心に使用の認可を求めたが、大本営ではなかなか認可せず、5月2日になって、一応準備をすることだけは認められた。奥山隊は第6航空軍の命令によって、5月8日唐瀬原を発って熊本健軍飛行場の傍にある三角兵舎に入った。唐瀬原を発つことこれで三回目である。その都度私物品を纏め送り先を書いて、留守担当の第1挺進団司令部に托している。
健軍に到着して、また訓練を重ねた。今度は飛行機は小型機で破壊は容易とみて、燃料集積所、指揮所、宿営地などの襲撃を目指した。5月17日、愈々実施について大本営の認可がおり、19日には飛行隊が浜松から健軍に到着し、攻撃計画も決定した。
敵が使用している飛行場は二つあって、北(読谷)の方が大きく、中(嘉手納)の方が小さかった。そこで、奥山隊長が率いる主力が八機に搭乗して読谷に、先任小隊長で副隊長格の渡部利夫大尉の率いる一部が、四機に搭乗して嘉手納に着陸することになった。奥山隊の総人員はサイパンを狙った当時の一三六名で、あの当時から一名の脱落者もない。3独飛の方は、途中で一部人員の入替えがあったが、諏訪部忠一大尉以下三二名である。重爆は一二機で、正操縦、副操縦、航法係、通信係の四名搭乗のものが四機、あとの八機は正副操縦二名という編成だった。
18:40健軍を離陸し、22:00に両目標に突入することとし、第6航空軍と第5航空艦隊は、義烈空挺隊が両飛行場を制圧している間に、総力を挙げて特攻攻撃を行うという手筈を整え、5月23日に決行ということになった。航空軍司令官の激励の辞も済み、乾盃も終わり愈々搭乗という段になって、海軍側から沖縄方面天候不良につき延期という連絡が入り、またもや挫折の悲運を味った。
翌24日、今度は天候もよく予定通り出撃した。22:00洋上に於て変針し、残波岬上空に第60戦隊の杉森機が照明弾を投下するので、それを標定して目標に進入することになっていたが、杉森機は照明弾投下という報告を発して消息を絶った。各編隊長機は変針、本島到着、只今突入という三回だけ電波を出す約束になっていたが、22:00になって只今突入という最初にして最後の報告を、知覧と健軍でキャッチした。戦果確認のため同行した第110戦隊長搭乗の草刈機は、22:25諏訪部隊着陸成功と報告した。
それから暫くたった23:45から、敵の緊急を告げる生文が次々と入ってきた。
「北飛行場異変あり」
「在空機は着陸するな」
「本島外の飛行場を利用せよ」
「母艦に着陸せよ」
「母艦の位置知らせ」
「残波岬の90度50浬に着艦せよ」
蜂の巣を突いたような騒ぎになった。
着陸さえ成功すれば、奥山隊の戦闘には絶対の信頼をおいていた。要はこの機を逸さず、如何に艦船攻撃の成果を挙げるかにあった。ところが、海軍側は24日昼に敵機動部隊の北上を知り、義烈の成果を待つことなく特攻機を出撃させ、25日には余力がなかった。25日第6航空群は一二〇機の特攻機を準備したが、天候不良で、離陸できたものは七〇機、突入と報告されたのは二四機に過ぎなかった。敵側の記録によると十三機の「カミカゼ」が十二隻の艦船に命中したとあるが、義烈の奮闘に対しては、余りにも少ない戦果だった。26日も天候は回復しなかった。
27日14:10、敵側の無線が
「強行着陸した日本軍全滅、本日10:00以降北飛行場使用支障なし」
と放送するのが傍受できた。結局24日夜半から27日朝まで北飛行場を封殺したのであるが、それを利用する成果の僅少だったことは、陸海軍の不一致とか天候の不良もあったが、戦力隔絶し、既に打つ手なしというのが実態であった。
なお、健軍を十二機離陸したが、四機は故障は航法未熟で引き返し南九州の各地に不時着した。草刈機の報告によれば、北飛行場に四機、中飛行場に二機着陸コースに入ったというが、米軍の記録によれば、着陸に成功して活躍したのは北飛行場一機だけで、数機が撃墜されたり、地上に激突して搭乗者は死んだとある。(田中賢一)