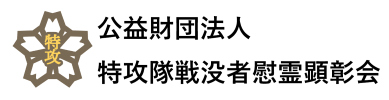第一編 特別攻撃隊の戦闘 序章 特攻作戦の概観
 5. 他の戦域での特攻作戦
5. 他の戦域での特攻作戦
先に述べた比島、沖縄作戦の間、他の戦域でも特攻攻撃が敢行されていた。
本土上空では、飛来するB -29に対し、防空戦闘隊が果敢な体当たり攻撃によって、衆人環視の中で敵機と共に砕け散っていた。太平洋を横行する敵艦隊、船団に対しては、回天が有効かつ効率のよい突撃を敢行した。南方資源要域では、残された陸軍飛行部隊が特攻隊を編成し、来攻する英・米艦隊に捨身の体当たり攻撃を敢行し、南方資源要域を敵手に委ねることはなかった。このうち七生神雷隊(飛行第61戦隊)のバリクパバン沖の攻撃に際しては、四名の海軍士官、下士官が参加し、うち衛藤少尉、尾川兵曹、大杉兵曹が体当たり戦没しているのが注目される。第一線では陸海一体となって作戦に従事していたのである。これらの特攻隊の活躍については、次章以下に詳述されているので省略し、特異な点だけを略記しておきたい。
B -29との対決は、日本防衛における最も重要な課題であったが、当時の日本にはこれに対抗し得る飛行機がなかった。震天制空隊は、機関砲などの重量物を全部取外すことによってB -29に対抗し得る飛行性能を得、体当たりによる撃墜を企図したものである。震天制空隊以外にも日本本土における体当たり攻撃は第二章に見られるように数多い。
昭和19年7月から12月にかけて、南満州は成都からのB -29の空襲にさらされた。満州に残された飛行部隊は少なく、満軍飛行部隊と協力して防衛に当たった。満州上空で体当たり戦没した者六名、この中に満軍蘭花特攻隊の二名が含まれる。さらに20年8月の終戦直後、侵攻するソ連軍に対し、今田達夫少尉以下一〇名が進攻ソ連戦車群に対し、体当たり攻撃を敢行した。かくの如く日本軍は友邦満州国防衛に関し死力を傾けて対処したのである。
前述の如く、防空に関しては最高性能の飛行機によらなければ成功は期し得ない。その開発努力は早くから進められていたが、基礎的な技術力、資源の枯渇のため成功しなかった。19年夏からエンジンは陸軍、機体は海軍の担任で秋水と呼ばれるロケット機の開発が進められた。最初の飛行試験は20年7月7日横須賀航空隊飛行場で行なわれた。秋水は高度一万メートルで九百キロの速度が出せると推定され、行動範囲は九六キロ、翼内装備の三〇ミリ砲二門でB-29に十分に対抗できると期待されていた。しかし、最初の飛行は失敗に終わり犬_豊彦海軍大尉は殉職した。この間にも最大の努力をもって秋水の生産、作戦基地の整備が進められていた。しかし、終戦までに七機が完成しただけで作戦には使用されずに終った。
日本軍は、進攻作戦によって敵基地を覆滅して防空を完うする考えであったので、防空戦闘機の開発に熱心でなかった。そのことが多くの特攻戦没者と未完成の試作機を生むことになった。