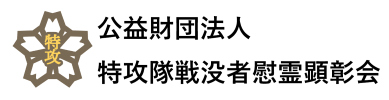第一編 特別攻撃隊の戦闘 序章 特攻作戦の概観
 2. 玉砕の島々
2. 玉砕の島々
昭和18月5月、アリューシャン列島の西端アッツ島の守備隊山崎保代大佐以下二、五〇〇名が18日間の激闘の末玉砕した。空・海の支援は実行不可能であり、大本営は空しくその敢闘を見守った。玉砕の報に国民は痛憤し、将兵は闘魂を燃やした。そのころ、南方の中部ソロモン、東部ニューギニアでは、空地の勇戦とともに凄惨な戦闘の様相が伝えられていた。全国有為の青年達が争って空中戦士たらんことを志し、航空隊あるいは飛行学校の門を入ったのもこのころである。

航空兵力劣勢下に、敵の進撃を食い止めるには、敵の海軍根拠地に敵艦隊を襲い、進攻して来る敵攻略船団の上陸前に破摧することが有効である。このころ特殊潜航艇は敵の警戒と制空下では使用が困難になっていた。黒木博司中尉、仁科関夫少尉はこれに替る人間魚雷「回天」の開発に熱中した。(第三章に詳述)後に㋹・震洋と呼ばれるボートに爆薬を積んで敵艦船に体当たりする水上特攻が、陸・海軍関係者によって発想されたのも昭和18年中期のことである。(第五章に詳述)
右のように、昭和18年は、敵の進撃をくいとめ、反撃の機を摑む手段として、将兵の心構えにおいても、兵器についても組織的な体当たり攻撃が準備された年と見ることが出来よう。事実、敵弾を受けて帰還不能となった操縦者は、最後の力を振りしぼって敵艦への体当たりを決行した。後に富獄特攻隊長となる西尾常三郎陸軍少佐は、当時ビルマ戦線飛行第98戦隊中隊長であったが、昭和18年11月9日の日記に次のように誌している。「11月初以来、ブーゲンビル方面の戦況、海軍の体当たり髣髴たり我当面する作戦に於ても正に体当たりすべし、決死隊を募ることあらば正に第一番にすべし、国家の安危なり生を求むべからず
通信手も要らず、機関手も要らず、射手も要らず、五〇〇瓩を抱きて計画的体当たりを用うべし決行すべし」
昭和18年末、連合軍はソロモン方面ではブーゲンビル島に上陸し、ニューギニアではダンピール海峡を突破した。ビルマ方面からの反撃も容易ならぬ様相を示した。しかし中部太平洋方面からの本格的反攻がさらに重大であった。
11月25日、マキン、タラワの守備隊四、六〇〇名が玉砕した。次いで昭和19年2月6日クエゼリン、ルオットの海軍部隊五、〇〇〇名、陸軍部隊一、〇〇〇名が玉砕した。この中に音羽正彦大尉(元朝香宮正彦王)もおられた。その痛憤のさめやらぬ2月25日エニウェトクの守備隊二、一〇〇名が玉砕した。全員大敵に屈することなく敢闘して日本軍の精華を発揮した。
このような戦況の中で、航空を志した者は逐次操縦技術を学び、さらに若者達がその後に続いていた。海軍では「回天」「蛟龍」等の計画が採用され、体当たりによる敵撃滅の計画が進められた。陸軍でも航空機による組織的体当たりの必要が論じられるようになった。