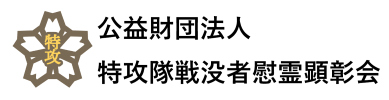第一編 特別攻撃隊の戦闘 第2章 陸海軍航空特別攻撃隊
 7. 本土決戦準備下の特攻隊
7. 本土決戦準備下の特攻隊
相次ぐ空襲と資源の枯渇のために飛行機の生産は低下したものの、本土防衛には航空特攻が最も期待されていた。
特攻機の生産は万難を排して進められ、壊れた飛行機はつぎはぎして特攻機に仕立てられた。
このようにして陸軍では、7 月20 日ごろ航空総軍隷下部隊として東日本の第1 航空軍に一般作戦機五百、特攻機六百。西日本の第6 航空軍に一般作戦機四百、特攻機一千。朝鮮の第5 航空軍に一般作戦機二百、特攻機五百が用意された。
特攻機の総計は二千百機であるが8 月末までには三千機に増勢される予定であった。
そして特攻機を掩護する一般作戦機も、最後には特攻となって敵艦上に炸烈するのである。
主力艦艇を失なった海軍は、水中特攻の「回天」「海龍」水上特攻の「震洋」などの部隊を数多く編成して要所に配備した。そして、遂には潜水服で敵の来襲をまつ「伏龍」まで現れた。
しかし、特攻の主力はやはり航空である。
終戦ごろの海軍の航空兵力は偵察部隊百四十、制空部隊千三十、対機動部隊特攻三百三十、対攻略部隊特攻三千七百二十五、計五千二百二十五機であった。これらは七十余カ所に分散されていた。
「桜花」は四三型が開発され、関東一帯の地上基地から発進するよう基地整備が進められていた。
このように9 月はじめを目標として、陸海軍の本土防衛態勢は着々と進められていた。
大本営は、この秋連合軍が約三千隻の艦船で南九州に来襲する場合、陸海軍約一万の航空特攻で約一千隻を撃沈破する念願であった。
そして、海中、海上特攻にもこれに連?する猛攻を期待した。
上陸した敵に対しては所在の部隊を結集する十人一殺の肉弾戦を展開するのである。
そのような作戦は、敗戦を受諾する戦争の終結によって実現しなかった。
最も警戒された特攻要員たる飛行機操縦者は早期に復員させられ、飛行機は焼かれた。